あんこの会
あんこがはみ出るくらい日々奮闘中のセラピストたちのブログ。 ぜひご一読を!
第1回 日本臨床作業療法学会 1日目
- 2014/03/25 (Tue)
- 未選択 |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
平成26年3月22日,23日
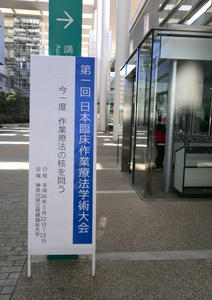
神奈川県保健医療大学にて
『今一度,作業療法の核を問う』と題して開催
昨年5月の湘南OT交流会のときから参加したいと思っていた学会
終始感動して帰ってきました.
やっぱり,OTが好きです.
ご講演の内容や写真の掲載などに問題がありましたらご連絡くださいませ.
1日目
受付を済ませると同時に,200冊限定先行販売の本
『作業で語る事例報告』を購入!!!
学会期中に完売笑 したので早く手に取ってよかった★★★
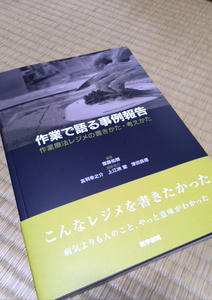
特別講演1
『作業に焦点を当てた実践を考える』
齋藤佑樹先生
①OTはわかりにくい?
どのOTも,作業療法の説明の仕方が違う.
様々な言葉で表現される『作業療法』
どの表現も間違っていない
でも,OTすべてを網羅する言葉で表現されることは多いとは言えない
なぜ?
OTはそもそも養成校時代から,手段に興味を持ってから目的を知る,という流れが多い
関心を持った手段の中に目的を見出す
陥るのは,アイデンティティクライシス
『作業療法ってなに?????』
何をするにも,
人の行動は
目的→手段
OTを学ぶ過程は
手段→目的+手段
では,原点に帰る
OTの目的ってなんだっけ?
これまたいろいろな表現があると思います.
でも,
行きつくのは『CLが健康になること』
どんな手段を用いても,
では,『健康』って?
様々な定義があるが
今回は園田恭一先生(1996年)
『生活や人生を高めていくという主体的制御能力の程度』
OTの目的
=『人が,大切な作業を通して,よりよい作業的存在になること』
OTは手段では語れない
目的のために,様々な手段を使えるのがOT
OTに大切なことは,『目標との連続性』
では,『作業ができる』とは?
カナダ作業モデルでは,
情緒・認知・体の3つを角にした三角形で人を表し,
さらに,その三角形(人)が丸(作業)と四角形(環境)と重なる
このモデルを横から見た図形では,人は作業を通して環境に関わる面積がほとんど
『作業ができる』には,環境との関連が重要
事例1:『自宅で入浴したい男性』(齋藤先生ご本人笑)
更衣・入浴動作評価,自宅環境の評価
自宅での動作自立→退院!!!
で,よいか?
この方には,娘をお風呂に入れるという役割があった.
この重要な役割はCLに生きがいをもたらす重要な意味のある作業
娘に安全に入浴させる,頭を洗う手助けをする,服を着せる,などの
一連の行為ができないとしたら,それは作業剥奪
個人的な作業のみでなく,そのCLが役割や価値を感じるものは何か?
PEOモデルでは,
人,作業,環境のそれぞれの丸が同じ大きさで表現され,重なり合い,
その中心が『作業遂行』
②なぜ,トップダウンなのか?
順番はそんなに大事?
面接(目的の確認)
→観察(手段の模索)
→検査(手段の模索)
→介入(手段の実行)
事例2:『美容室で髪を切る女性』(齋藤先生の娘さん★)
美容室で・・・
→毛先はどうしますか?
→色はどうしますか?
→どんな髪型にしたいですか?
毛先も色も決まった後で,髪型を考える???
変な髪型になったらどうする?笑
→どんな髪型にしたいですか?(目的)
→毛先はどうしますか?(手段)
→色はどうしますか?(手段)
『なぜ』を考える間もなく,トップダウンがごく自然でしょう
OTには,CLの主体性が何よりも大切
目的なしに手段は存在しない
③面接・観察・検査のポイントは?
面接の目的:OTの役割を知ることができる
CLとOTの役割を尊重し合う信頼関係を構築できる
CLが『作業的存在としての自分』に初めて出会う時間である
(CL自身が『作業』の視点で自分に出会う)
SDM
『CLのほうが知っていること(作業的ニーズ,作業歴,心理状態,役割)』と
『OTのほうが知っていること(作業の持つ力,手段)』
をすり合わせる
目標は,その人特有の文脈を取り入れた表現で
『家族と一緒に,和室で食事をする』とか
でも,作業に焦点を当てなきゃ!と必死になるよりは,まず思いを受け止めよう
機能固執,意欲低下,訓練拒否
CLは日々様々な心理状態にさらされている
これらの感情は当たり前
このような状態にであったとき,まずはリーズニングにつなげる
観察≠動作分析
作業遂行上の課題は何か?
見極めるポイントとは3つ
①実際の環境に近づける
②見たままを観察する
作業遂行している状態
→遂行の様子をそのまま言葉で表現する
→人・環境・作業を同じ比重で評価する
③CLがその場面の目的を理解している
CLにとっては,久しぶりに大切な作業ができる時間
OTにとっては,作業の質を評価できる時間
そこの理解を共有していないと,ただの失敗体験につながるリスクが高い
せっかくの信頼関係やCLの意欲喪失に
検査や測定の目的は,OBPのためだけじゃない
・リスク管理や連携のため(医療人として)
・『作業の可能化(人が作業を通して環境に結びつくことができること)』のため
作業ができなくなっている原因をあらゆる面から考えるための手段の一つ
OTとは,作業に焦点を当てた介入ができる職種
目的と手段が区別できれば,OTは曖昧じゃない
ワークショップ
『トップダウンの作業療法~真のニーズを探る~』
藤本一博先生
目標が曖昧で具体性が低い,動機づけが弱い
=CLは,やりたくない
→CLが,意味を感じるには?
大事なのは,ニーズの抽出
トップダウン=OBPの手順
初回面接の様子をいくつか提示
①CLは,自分のニーズを検討していた?
日本は文化的側面からも,『自分』のことを検討した経験が少ない人が多い.
『自分よりも人のため』(利他主義)
②予後予測は正しくできていた?
③CLはいくつもの選択肢から選んでいた?
『1:機能を治して元通りになる』
『2:諦めて人生を終える』
の2択しか存在しなかった可能性は?医学的な知識がないと全か無になりやすい
ポイントは
①一歩踏み込んで,多面的にとらえる必要性
人は環境に埋め込まれている.一つの情報をうのみにしてはいけない
他の要素は?家族は?
ライフスタイルは9つの視点で評価・・・
ADL,健康維持,安全,環境適応,移動,幸福,自由時間,お金,他者との関係
②OTの専門スキルって?
OTのしていることは,他職種ができることも多い
OTにしかできないこと
1.各動作を一緒にやってみる
2.他職種やご家族から作業に即した情報を収集する
3.各要因を総合的に分析する(MOHOで作業適応分析,CMOPで作業可能化分析)
OTの専門スキル=評価の実施スキル+分析スキル
また,面接での自己開示は重要
これにより互いの距離を縮め,信頼関係の構築を促進する
藤本先生のことは本当に大好きなんですが,書面ではどうにも表現しきれません笑
ぜひ直接お話を聞かれることをお勧めします★
1日目午前の部終了
ランチは友利先生,上江洲先生がお弁当を配ってくださいました♪
午後は,口述,ポスター発表から
みなさま素敵すぎて,聞きたい内容がてんこもり.
聞きたくても時間が重なっていて聞けない演題や
質問者が待っていて時間が足りずに話せなかった演題も多くて.そこは残念.
でも,みんなOT大好きなんだな笑
特別講演2 竹林崇先生
『脳卒中上肢麻痺に対する作業を用いた訓練』
意味のある作業の実現
そのためにも,やっぱり可能な限り元の機能に近づけたい
リハビリって,そもそも社会復帰とか再建
手のリハビリ
・麻痺手に対する量的訓練
・課題指向型訓練
・トランスファーパッケージ
一番重要なのはトランスファーパッケージ
=麻痺手の機能を上げることではなく,CLの行動自体を変えること
行動変容には,報酬が大事
報酬とは,この場合,目標の実現や達成感を得ること
それによりドーパミンが分泌される
新たな行動を学習する条件は,
大脳皮質が賦活し,線条体でスパイクが起き,ドーパミンがおくられたとき.
報酬があると,線条体や扁桃体,前頭前野に有意な変化が起きる
目標を決定するときには,ただ質問すればよいか?
麻痺した手を使用していない,
また長年腹側路を使用していないCLは,記憶の想起も不十分になる
現在の条件下で使用している四肢がないと,想起されない
→目標決定には呼び水,ツール,声掛け(想起のヒントになるもの)が必要
発症して180日経過した後に先生のもとで機能訓練実施
訓練期間終了後も改善しつづけたCLさんたち
その行動を支えるものは,長期に及んだ報酬効果
・課題指向型訓練と機能指向型訓練
脳は使用依存的にネットワークを強化する
課題指向型訓練は,できるだけ実際の生活に近い課題を提示するもの
同じ動作をしても,脳は異なるルートを使う
・リーチ動作のみ行う
・目的物を用意してリーチ動作を行う
人は手を使用するとき,ほとんど目的物がある
生活により必要なダイナミクスは,目的物があるほう.
課題指向型訓練
・基本はTrial&Error.多少のエラーはシナプスの作り変えには必要
・難易度の調整が重要.指標には,quallity of movement 3.5~4が適切と言われる
<難易度調整の方法>
同じ道具を使って,空間的な広がりを使う
異なる道具を使う
肢位を変える
失敗体験が増えると行動抑制が起こるので要注意
・2種類を使い分ける.
機能がある程度改善してから目的的な訓練を行った方が報酬が.
shaping(作業の手段的利用)
Task Practice(作業の目的的利用)
・・・脳卒中のサルで研究
A群:すぐ取れる場所にある餌を毎日自力摂取
B群:何回か試行錯誤しないと取れない場所にある餌を毎日自力摂取
A群は,一次運動野の領域は減少,B群は3%前後拡大
一番重要なトランスファーパッケージの実際
・麻痺手を使うという約束
良くなったら,何がしたい???
思いつかない人が多い.
呼び水も出して,よくよく考えてもらう.自分と向き合ってもらう
そして,機能は使わないとなくなるので日常生活で使ってもらう
・問題解決技法
両手動作,麻痺手での動作,健側手での動作・・・
落としどころを決める
例:普段は使いたくない.でもスイーツを食べるときは麻痺手で食べる!など
でも,CLは使える手だとしても,どの場面でどういうふうに使えばいいかわからない
→OTが伝える.先生は,すべての記録を残し,1冊の教科書としてお渡ししている
意味のある作業の実現に向けて,セラピストは声は出すが手は出さない
すごい内容を1時間でお話されましたので全く網羅できてなくて(TT)
すみません.
竹林先生はこの3連休,怒涛のメニューをこなされました笑
大好きです.
懇親会
お会いしたかった方々にお会いできました(TT)(TT)
湘南OTで初めてお会いしてずっとツイッターでやりとりしていた方々も
ツイッターでやりとりはしていたけど初対面でお会いする方も
全くの初対面の方も
みなさま大好きです.
2日目も楽しむぞー!!

あんこ
神奈川県保健医療大学にて
『今一度,作業療法の核を問う』と題して開催
昨年5月の湘南OT交流会のときから参加したいと思っていた学会
終始感動して帰ってきました.
やっぱり,OTが好きです.
ご講演の内容や写真の掲載などに問題がありましたらご連絡くださいませ.
1日目
受付を済ませると同時に,200冊限定先行販売の本
『作業で語る事例報告』を購入!!!
学会期中に完売笑 したので早く手に取ってよかった★★★
特別講演1
『作業に焦点を当てた実践を考える』
齋藤佑樹先生
①OTはわかりにくい?
どのOTも,作業療法の説明の仕方が違う.
様々な言葉で表現される『作業療法』
どの表現も間違っていない
でも,OTすべてを網羅する言葉で表現されることは多いとは言えない
なぜ?
OTはそもそも養成校時代から,手段に興味を持ってから目的を知る,という流れが多い
関心を持った手段の中に目的を見出す
陥るのは,アイデンティティクライシス
『作業療法ってなに?????』
何をするにも,
人の行動は
目的→手段
OTを学ぶ過程は
手段→目的+手段
では,原点に帰る
OTの目的ってなんだっけ?
これまたいろいろな表現があると思います.
でも,
行きつくのは『CLが健康になること』
どんな手段を用いても,
では,『健康』って?
様々な定義があるが
今回は園田恭一先生(1996年)
『生活や人生を高めていくという主体的制御能力の程度』
OTの目的
=『人が,大切な作業を通して,よりよい作業的存在になること』
OTは手段では語れない
目的のために,様々な手段を使えるのがOT
OTに大切なことは,『目標との連続性』
では,『作業ができる』とは?
カナダ作業モデルでは,
情緒・認知・体の3つを角にした三角形で人を表し,
さらに,その三角形(人)が丸(作業)と四角形(環境)と重なる
このモデルを横から見た図形では,人は作業を通して環境に関わる面積がほとんど
『作業ができる』には,環境との関連が重要
事例1:『自宅で入浴したい男性』(齋藤先生ご本人笑)
更衣・入浴動作評価,自宅環境の評価
自宅での動作自立→退院!!!
で,よいか?
この方には,娘をお風呂に入れるという役割があった.
この重要な役割はCLに生きがいをもたらす重要な意味のある作業
娘に安全に入浴させる,頭を洗う手助けをする,服を着せる,などの
一連の行為ができないとしたら,それは作業剥奪
個人的な作業のみでなく,そのCLが役割や価値を感じるものは何か?
PEOモデルでは,
人,作業,環境のそれぞれの丸が同じ大きさで表現され,重なり合い,
その中心が『作業遂行』
②なぜ,トップダウンなのか?
順番はそんなに大事?
面接(目的の確認)
→観察(手段の模索)
→検査(手段の模索)
→介入(手段の実行)
事例2:『美容室で髪を切る女性』(齋藤先生の娘さん★)
美容室で・・・
→毛先はどうしますか?
→色はどうしますか?
→どんな髪型にしたいですか?
毛先も色も決まった後で,髪型を考える???
変な髪型になったらどうする?笑
→どんな髪型にしたいですか?(目的)
→毛先はどうしますか?(手段)
→色はどうしますか?(手段)
『なぜ』を考える間もなく,トップダウンがごく自然でしょう
OTには,CLの主体性が何よりも大切
目的なしに手段は存在しない
③面接・観察・検査のポイントは?
面接の目的:OTの役割を知ることができる
CLとOTの役割を尊重し合う信頼関係を構築できる
CLが『作業的存在としての自分』に初めて出会う時間である
(CL自身が『作業』の視点で自分に出会う)
SDM
『CLのほうが知っていること(作業的ニーズ,作業歴,心理状態,役割)』と
『OTのほうが知っていること(作業の持つ力,手段)』
をすり合わせる
目標は,その人特有の文脈を取り入れた表現で
『家族と一緒に,和室で食事をする』とか
でも,作業に焦点を当てなきゃ!と必死になるよりは,まず思いを受け止めよう
機能固執,意欲低下,訓練拒否
CLは日々様々な心理状態にさらされている
これらの感情は当たり前
このような状態にであったとき,まずはリーズニングにつなげる
観察≠動作分析
作業遂行上の課題は何か?
見極めるポイントとは3つ
①実際の環境に近づける
②見たままを観察する
作業遂行している状態
→遂行の様子をそのまま言葉で表現する
→人・環境・作業を同じ比重で評価する
③CLがその場面の目的を理解している
CLにとっては,久しぶりに大切な作業ができる時間
OTにとっては,作業の質を評価できる時間
そこの理解を共有していないと,ただの失敗体験につながるリスクが高い
せっかくの信頼関係やCLの意欲喪失に
検査や測定の目的は,OBPのためだけじゃない
・リスク管理や連携のため(医療人として)
・『作業の可能化(人が作業を通して環境に結びつくことができること)』のため
作業ができなくなっている原因をあらゆる面から考えるための手段の一つ
OTとは,作業に焦点を当てた介入ができる職種
目的と手段が区別できれば,OTは曖昧じゃない
ワークショップ
『トップダウンの作業療法~真のニーズを探る~』
藤本一博先生
目標が曖昧で具体性が低い,動機づけが弱い
=CLは,やりたくない
→CLが,意味を感じるには?
大事なのは,ニーズの抽出
トップダウン=OBPの手順
初回面接の様子をいくつか提示
①CLは,自分のニーズを検討していた?
日本は文化的側面からも,『自分』のことを検討した経験が少ない人が多い.
『自分よりも人のため』(利他主義)
②予後予測は正しくできていた?
③CLはいくつもの選択肢から選んでいた?
『1:機能を治して元通りになる』
『2:諦めて人生を終える』
の2択しか存在しなかった可能性は?医学的な知識がないと全か無になりやすい
ポイントは
①一歩踏み込んで,多面的にとらえる必要性
人は環境に埋め込まれている.一つの情報をうのみにしてはいけない
他の要素は?家族は?
ライフスタイルは9つの視点で評価・・・
ADL,健康維持,安全,環境適応,移動,幸福,自由時間,お金,他者との関係
②OTの専門スキルって?
OTのしていることは,他職種ができることも多い
OTにしかできないこと
1.各動作を一緒にやってみる
2.他職種やご家族から作業に即した情報を収集する
3.各要因を総合的に分析する(MOHOで作業適応分析,CMOPで作業可能化分析)
OTの専門スキル=評価の実施スキル+分析スキル
また,面接での自己開示は重要
これにより互いの距離を縮め,信頼関係の構築を促進する
藤本先生のことは本当に大好きなんですが,書面ではどうにも表現しきれません笑
ぜひ直接お話を聞かれることをお勧めします★
1日目午前の部終了
ランチは友利先生,上江洲先生がお弁当を配ってくださいました♪
午後は,口述,ポスター発表から
みなさま素敵すぎて,聞きたい内容がてんこもり.
聞きたくても時間が重なっていて聞けない演題や
質問者が待っていて時間が足りずに話せなかった演題も多くて.そこは残念.
でも,みんなOT大好きなんだな笑
特別講演2 竹林崇先生
『脳卒中上肢麻痺に対する作業を用いた訓練』
意味のある作業の実現
そのためにも,やっぱり可能な限り元の機能に近づけたい
リハビリって,そもそも社会復帰とか再建
手のリハビリ
・麻痺手に対する量的訓練
・課題指向型訓練
・トランスファーパッケージ
一番重要なのはトランスファーパッケージ
=麻痺手の機能を上げることではなく,CLの行動自体を変えること
行動変容には,報酬が大事
報酬とは,この場合,目標の実現や達成感を得ること
それによりドーパミンが分泌される
新たな行動を学習する条件は,
大脳皮質が賦活し,線条体でスパイクが起き,ドーパミンがおくられたとき.
報酬があると,線条体や扁桃体,前頭前野に有意な変化が起きる
目標を決定するときには,ただ質問すればよいか?
麻痺した手を使用していない,
また長年腹側路を使用していないCLは,記憶の想起も不十分になる
現在の条件下で使用している四肢がないと,想起されない
→目標決定には呼び水,ツール,声掛け(想起のヒントになるもの)が必要
発症して180日経過した後に先生のもとで機能訓練実施
訓練期間終了後も改善しつづけたCLさんたち
その行動を支えるものは,長期に及んだ報酬効果
・課題指向型訓練と機能指向型訓練
脳は使用依存的にネットワークを強化する
課題指向型訓練は,できるだけ実際の生活に近い課題を提示するもの
同じ動作をしても,脳は異なるルートを使う
・リーチ動作のみ行う
・目的物を用意してリーチ動作を行う
人は手を使用するとき,ほとんど目的物がある
生活により必要なダイナミクスは,目的物があるほう.
課題指向型訓練
・基本はTrial&Error.多少のエラーはシナプスの作り変えには必要
・難易度の調整が重要.指標には,quallity of movement 3.5~4が適切と言われる
<難易度調整の方法>
同じ道具を使って,空間的な広がりを使う
異なる道具を使う
肢位を変える
失敗体験が増えると行動抑制が起こるので要注意
・2種類を使い分ける.
機能がある程度改善してから目的的な訓練を行った方が報酬が.
shaping(作業の手段的利用)
Task Practice(作業の目的的利用)
・・・脳卒中のサルで研究
A群:すぐ取れる場所にある餌を毎日自力摂取
B群:何回か試行錯誤しないと取れない場所にある餌を毎日自力摂取
A群は,一次運動野の領域は減少,B群は3%前後拡大
一番重要なトランスファーパッケージの実際
・麻痺手を使うという約束
良くなったら,何がしたい???
思いつかない人が多い.
呼び水も出して,よくよく考えてもらう.自分と向き合ってもらう
そして,機能は使わないとなくなるので日常生活で使ってもらう
・問題解決技法
両手動作,麻痺手での動作,健側手での動作・・・
落としどころを決める
例:普段は使いたくない.でもスイーツを食べるときは麻痺手で食べる!など
でも,CLは使える手だとしても,どの場面でどういうふうに使えばいいかわからない
→OTが伝える.先生は,すべての記録を残し,1冊の教科書としてお渡ししている
意味のある作業の実現に向けて,セラピストは声は出すが手は出さない
すごい内容を1時間でお話されましたので全く網羅できてなくて(TT)
すみません.
竹林先生はこの3連休,怒涛のメニューをこなされました笑
大好きです.
懇親会
お会いしたかった方々にお会いできました(TT)(TT)
湘南OTで初めてお会いしてずっとツイッターでやりとりしていた方々も
ツイッターでやりとりはしていたけど初対面でお会いする方も
全くの初対面の方も
みなさま大好きです.
2日目も楽しむぞー!!
あんこ
PR
あんこカウンター
相互リンク
最新記事
(09/21)
(09/03)
(06/04)
(06/01)
(06/01)
(05/27)
(05/27)
(05/13)
(05/11)
月ごとの記事のまとめ
最新コメント
[05/28 Shizuka]
[05/27 志木田孝治]
[12/10 エキセントリック]
[10/16 NONAME]
[09/13 カコ]



この記事へのコメント